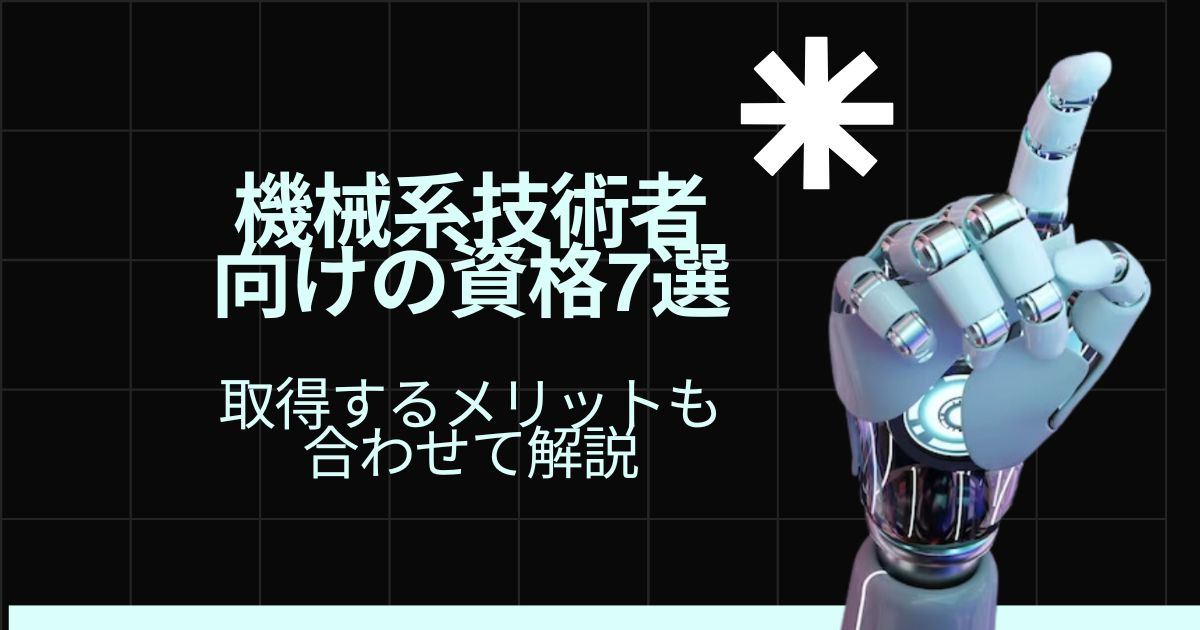
機械系技術者向けの資格7選|取得するメリットもあわせて解説
機械技術者として働く中で、スキルアップやキャリアアップを目指して資格取得を検討する人は少なくありません。
本記事では、実際に役立つ機械技術者におすすめの資格7選を取り上げ、それぞれの特徴や取得するメリットについて解説します。
機械系技術者向けの資格7選
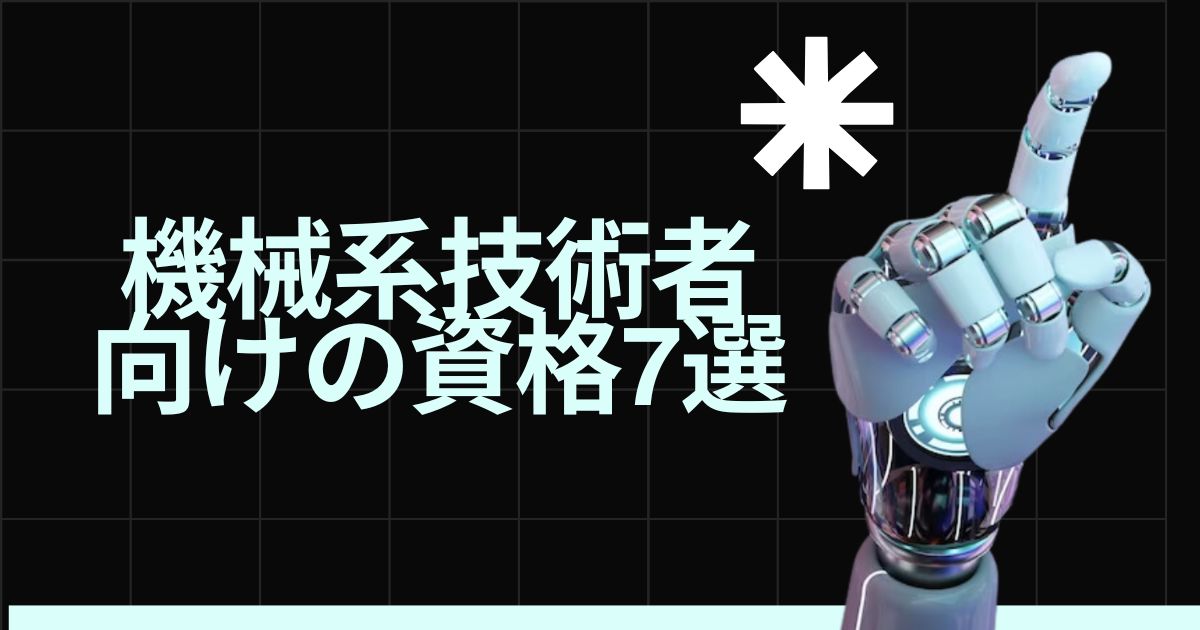
機械技術者の仕事に役立つ資格は数多くありますが、その中から厳選したおすすめの資格をご紹介します。
資格取得に必要な知識や経験、役立つ場面や難度などがそれぞれ異なるので、業務内容や目指すキャリアなどを踏まえて選択してください。
技術士(機械部門)
技術士(機械部門)は、公益社団法人日本技術士会が運営する、文部科学省管轄の国家資格です。
科学技術に関連する専門知識に加え、高い応用能力や豊富な実務経験、公益確保に役立つ倫理観を備えた技術者を育成するために設けられた資格で、機械部門は全21部門のうちの一つです。試験では、材料力学、機械力学、振動工学、制御工学、工業熱力学、伝熱工学、流体力学などの科目が出題されます。
毎年1回1次試験と2次試験が行われており、1次試験に合格すると修習技術者となって、所定の手続きにより技術士補を名乗ることができますが、2次試験を通過しなければ技術士にはなれません。
1次試験の合格率は年によって異なりますが、30~50%程度です。
一定の学習が必要ですが、計画的に取り組めば取得を目指すことができます。
一方、2次試験は合格率11%前後といわれており、高難度の資格として知られています。
それだけに2次試験まで合格すれば機械分野のスペシャリストであることを証明できます。
1次試験の受験資格は特にありませんが、2次試験は技術士補として技術士のもとで4年を超える実務経験を積む必要があるので、知識だけでは取得できない資格でもあります。
技術士(機械部門)の1次試験には直近5~7年間程度の過去問の徹底学習が有効です。
合格に必要な学習時間は、技術知識の量などで大きく異なりますが、400時間程度ともいわれています。
つまり毎日2時間の学習を続けても半年以上かかるため、長期的な覚悟を持って計画的に進めることをおすすめします。
機械・プラント製図技能士
機械やプラントの製図技能を評価する国家資格で、厚生労働省が管轄、中央職業能力開発協会が運営しています。
機械の保守などを行う際に有用な資格で、学科試験と実技試験があります。
学科試験では製図一般、材料、材料力学一般、溶接一般、関連基礎知識のほか、機械製図法、もしくはプラント配管製図法などから出題されます。
実技試験は機械製図手書き作業、機械製図CAD作業、プラント配管製図作業の3種類から選択可能です。
1級から3級までの等級があり(プラント配管製図作業は1級と2級のみ)、3級は学歴や年齢などの制限なく誰でも受験可能です。
2級は3級取得か実務経験2年以上、1級は2級合格後の実務経験2年以上か3級合格から実務経験4年以上、または7年以上の実務経験がなければ受験できません。
各試験に合格すると機械・プラント製図技能士を名乗ることが可能となるほか、国家資格なので転職などの場面で役立ちます。
機械・プラント製図技能士の過去の試験問題は、中央職業能力開発協会公式サイト内の「技能検定試験問題公式サイト」で閲覧できます。
また、過去の試験問題を解説する書籍も出ているので、ぜひご利用ください。
電気主任技術者(電験)
電気事業法という法律に基づいた、電気工作物の工事、維持、運用などに関する国家資格です。
機械の保守などを行う際に有用な資格で、取得すると事業用電気工作物の工事や維持、運用などの監督を行えるようになります。
第一種から第三種までがあり、第三種は電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物、第二種は17万ボルト未満の事業用電気工作物、第一種はすべての事業用電気工作物の工事に関する保安監督が可能です。
比較的難度が低いとされる第三種でも合格率10%前後、低い年は6%程度と、かなり高難度な資格です。
これほど難度が高い理由のひとつに、過去問と類似する問題はあるものの、同じ問題は一切出ないことがあります。
そのため、覚えるだけの学習では合格できない場合が多く、基礎知識の理解が要求されます。
第三種は1次試験のみですが、第二種と第一種では2次試験もあります。
1次試験は理論、電力、機械、法規の4科目で構成されており、科目ごとに合格認定されます。
合格した科目は3年以内なら有効なので、例えば1年目に理論と電力で合格した場合、2年目は機械と法規だけを受ける選択も可能です。
電気主任技術者第三種を取得するために必要な学習時間は、知識や経験によって大きく異なりますが、一般的に約1,000時間とされています。つまり、毎日3時間ほど学習しても1年前後かかるため、短期間での習得は難しいといえます。
合格を真剣に目指すのであれば、計画的な学習を進めてください。
電気関係の資格ではありますが、機械設備の保守などでも電気工事を伴うことは珍しくないので、取得しておくと役立ちます。
また、難度が高い資格であることから、転職時のアピール材料としても有効です。
電気通信主任技術者
電気工作物の工事、維持、運用などに関する国家資格で、総務省が管轄、一般財団法人 日本データ通信協会が運営しています。
「伝送交換主任技術者試験」と「線路主任技術者試験」の2種類があり、受験資格は特にないので、誰もが資格取得に挑むことができます。
試験問題は伝送交換主任技術者試験の場合、電気通信システム、伝送交換設備及び設備管理、法規の3科目から出題されます。
一方、線路主任技術者試験の出題範囲は、電気通信システム、線路設備及び設備管理、法規の3科目です。
伝送交換主任技術者試験に合格すると、事業用電気通信設備の工事、維持、運用時の監督を務めることができます。
また、線路主任技術者試験に合格すると、電気通信事業用の線路設備や、それに付随する設備の工事・維持の監督が可能です。
IoT技術の普及・発展によってスマートメーターなど電気通信技術に関連する業務が増加しているため、電気通信主任技術者の資格取得が推奨されます。
例年の合格率は20~35%とされており、電気通信主任技術者の資格取得は難度高めですが、IoT関連機器の設計に携わるエンジニアであれば非常に有用な資格です。
学習方法としては過去問の徹底学習が有効です。一般財団法人 日本データ通信協会の公式サイト内に直近数年分の過去問と回答が記載されているので、ぜひご参照ください。
電気工事施工管理技士
建設工事の管理や安全・品質保持に関する国家資格で、国土交通省が管轄、一般財団法人建設業振興基金が運営しています。
機械設計者が建設分野での業務に携わる際に有用で、1級と2級があり、1級なら特定の建設業において、営業所専任技術者の業務を担当でき、2級なら一般建設業における営業所の専任技術者になることが可能です。
1級、2級ともに第一次検定と第二次検定があり、第二次検定を受けるためには第一次検定を通過しなければなりません。
2級の近年の合格率は、第一次検定、第二次検定ともに概ね40~60%台の範囲で増減しています。
合格率を見ると高難度の資格試験とは考えにくいですが、2級の一次検定合格に必要な学習時間は50~100時間、二次検定合格は20~50時間といわれており、ある程度の時間を要します。
数値的に見て半数程度の受験者は不合格となることを踏まえ、油断なく学習しましょう。
学習方法としては、過去問を繰り返し解いて傾向を把握しつつ、必要な知識を身につけることをおすすめします。
また、過去問をおぼえるのではなく、基礎からきちんと理解しておくと類似問題に惑わされることなく対応できます。
機械設計技術者試験
機械設計に関する知識と技術力を評価する民間資格で、一般社団法人 日本機械設計工業会が運営しています。
機械エンジニアの技術力の把握に役立ち、エンジニアの地位向上や能力向上、さらに日本の機械産業の底上げなど、複数の目的を有しています。
1~3級が設定されており、3級は機械工学の基礎、2級は基礎を踏まえた設計技能、1級は機械設計者として高い知識と総合能力を問う問題が出されます。
3級には受験資格の制限はありませんが、2級は学歴に応じた実務経験年数がなければ受験できません。
ただし、3級を取得していれば2級受験にあたって必要な実務経験年数は軽減され、1級も2級取得によって軽減されます。
3級の出題内容は、機構学・機械要素設計や機械力学、制御工学や工業材料、材料力学や流体・熱工学、工作法や機械製図です。
2級は機械要素設計分野や熱流体分野、メカトロ分野や力学分野、材料・加工分野や環境安全分野、応用・総合の範囲から出題されます。
1級では設計管理関連課題や機械設計基礎課題、環境経営関連課題や実技課題のほか、小論文の作成も要求されます。
一般社団法人 日本機械設計工業会の発表によれば、令和5年の合格率は1級で36.4%、2級で40.8%、3級で47.1%であり、3級は半数程度の人が合格する一方、1級は3分の1程度しか合格できないことが分かります。
合格に向けた学習時間は技術知識の有無で異なりますが、3級合格のためには200~300時間、2級は400時間、1級は300時間程度が必要といわれています。
学習方法としては、参考書や過去問を通じて出題科目の基礎を理解することが重要です。
主体的な学習が必要な資格試験なので、計画を立てて試験に臨みましょう。
CAD利用技術者試験
2次元および3次元のCADソフトウェアの利用技術を評価する資格で、一般社団法人コンピュータ教育振興協会が運営しています。CAD(Computer Aided Design)エンジニアを育成するために設立された資格試験で、取得することによって、図面作成スキルの証明ができます。
大きくは2次元CAD利用者技術試験と3次元CAD利用者試験に分類されます。また、2次元CAD利用者技術試験は基礎、2級、1級と3段階に分かれており、3次元CAD利用者技術試験は2級、準1級、1級の3段階に分類されます。
近年は2次元CADより3次元CADの需要が多いので、受験するなら3次元CAD利用者技術試験がおすすめです。
3次元CAD利用者技術試験2級には受験資格がないので誰でも受けられますが、準1級と1級は2級合格が必須条件となるため、
順序的にまず2級を受けざるを得ません(2級と準1級、1級の同時受験は可能)。
3次元CAD利用者技術試験2級の合格率は40~70%台と年によってばらつきが大きいものの、半数以上の人が合格している年が
多く見られます。そのため、事前にしっかり学習すれば取得できる資格です。
試験では公式ガイドブックに準拠した問題が出るので、公式ガイドブックの入手は必須です。
勉強方法としては公式ガイドブックの情報を理解すること、過去問の繰り返しで傾向把握と徹底理解を進めることをおすすめします。
準1級も難度は2級とさほど変わりませんが、1級の合格率は例年20~30%台で難度が上がるため、1級受験の際は時間をかけて計画的に学習する必要があります。
機械系の資格を取得するメリット
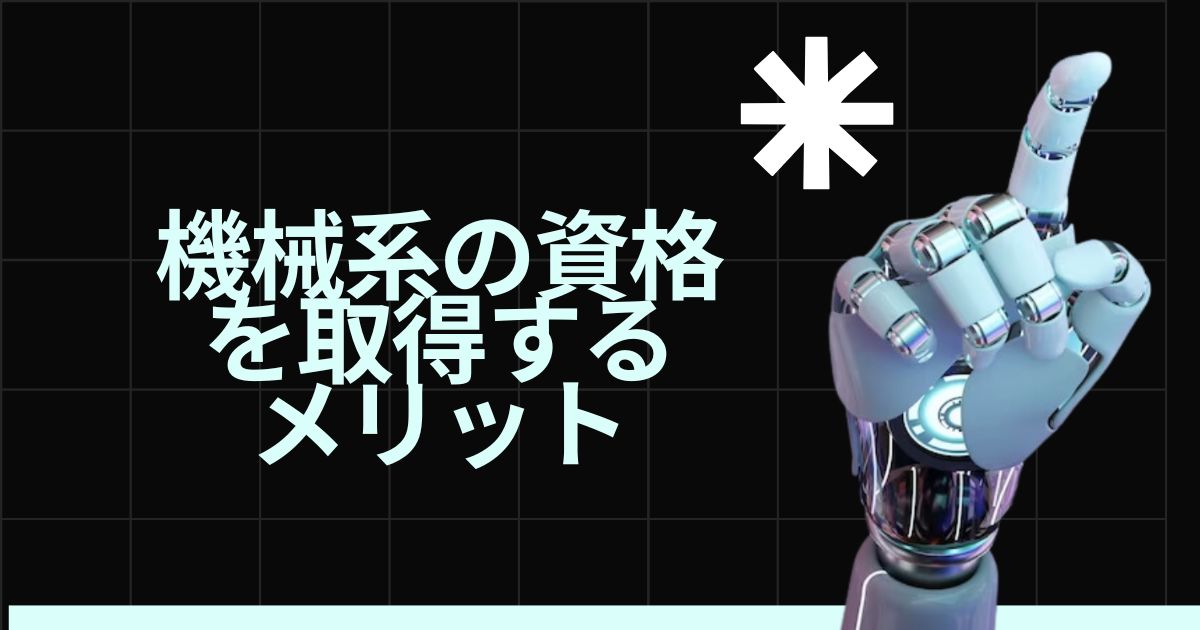
資格を取るには、申し込みや受験費用、さらに勉強の時間が必要です。それでも、資格を取得することで得られるメリットはたくさんあります。ここでは、代表的なメリットについて分かりやすく解説します。
学ぶことで知識を深められる
エンジニアとして働く上で、学び続けることは欠かせません。
しかし、忙しい日々の中では、新しい知識を学ぶ時間が取れないこともあります。
そんな時、資格取得を目指すことで、学び直すきっかけを作れます。
資格取得に向けて学習する中で、新たな知識を得たり、これまで浅かった知識を深めることができます。
また、試験勉強を通じて知識が体系的に整理され、エンジニアとしてさらに成長する機会につながります。
知識・スキルの客観的証明になる
資格は、その分野についての知識や技術を持っていることの証明になるものです。
また、資格取得によって、技能向上に前向きで、計画的に学習する能力があり、決めた目標にきちんと到達した人、
という信頼感にもつながります。
転職で有利に働く
資格の取得は、転職にも有利に働きます。知識やスキル、経験などの証明になり、採用担当者の信頼も得やすくなるでしょう。
本記事に記載した資格はいずれも有効ですが、特に技術士や電気主任技術者三種などの高難度資格を持っていれば、エンジニアとして非常に高い知識を有していること、高難度試験をクリアした努力家であることなどが示せるため、大きなアピール材料になります。
機械系エンジニアの転職なら「メイテックネクスト」

弊社はエンジニア専門の転職支援サービスとして業界No.1クラスの求人数を扱っています。
また、各企業の採用担当者との交流が密接で、企業の内情を踏まえたアドバイスが可能です。
これによって書類選考や面接を通過しやすくなり、転職希望者と企業の双方に最適なご提案を行うことができます。
弊社の転職サービスを支えているのは豊富な知識と経験を持つ転職支援コンサルタントです。
半数以上がメーカーの技術系業務を経験していますので、エンジニアの気持ちに寄り添いながら、
企業の意志も尊重したサポートができます。
エンジニアとして転職するのであれば、ぜひ弊社にご相談下さい。
機械系エンジニアの転職成功事例
電気・電子メーカー(機械設計)600万円⇒大手電機・精密メーカー(機械設計)700万円
【転職者の声】
大手企業からベンチャー企業に飛び込みましたが、スピード感のある製品開発に携われるメリットを感じる一方で、
品質面の軽視が感じられて転職を検討。面談時には経験概要だけでなくやりがいを深掘りいただき、
『企画したモノが試作~量産と製品が形になった時』『組合せが煩雑な製品開発』という点を改めて認識することができました。
その上で、ある程度の企業規模、新しい事に挑戦・チャレンジ出来る環境、興味のある製品群、といった点を考慮した求人を
紹介いただきました。面接対策はもちろん実施いただきましたが、企業情報の都度の共有などを含め、内定獲得に向けて、
お互いに連携を取りながら進めていく感覚でした。その結果、内定を獲得した時点で気持ちは固まっており、
即日入社を決断して企業にお伝えすることができました。
この記事の寄稿者
機械エンジニアとして働く人に向けて、おすすめの資格を厳選して紹介し、特徴や難度、学習方法などをまとめました。資格取得に挑めば自分の知識やスキルを高められるだけでなく、社内での地位向上にもつながり、転職時のアピール材料にもなります。ぜひこの機会に資格取得をご検討ください。

- 高見澤希
