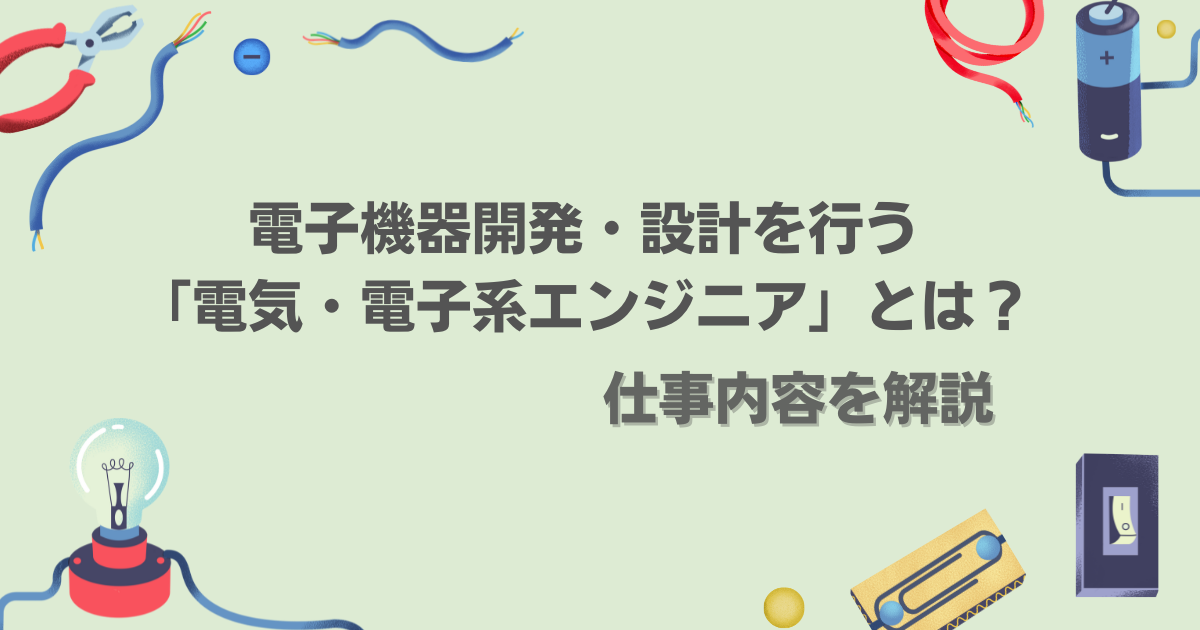
電子機器開発・設計を行う「電気・電子系エンジニア」とは?仕事内容を解説
電気・電子系エンジニアは、スマートフォンや家電、自動車など、私たちの生活を支えるさまざまな分野で活躍しています。
本記事では、電気・電子系エンジニアの業務内容や必要なスキル、IT・機械系エンジニアとの違いについて詳しく解説します。
電子機器開発・設計を行う「電気・電子系エンジニア」とは?
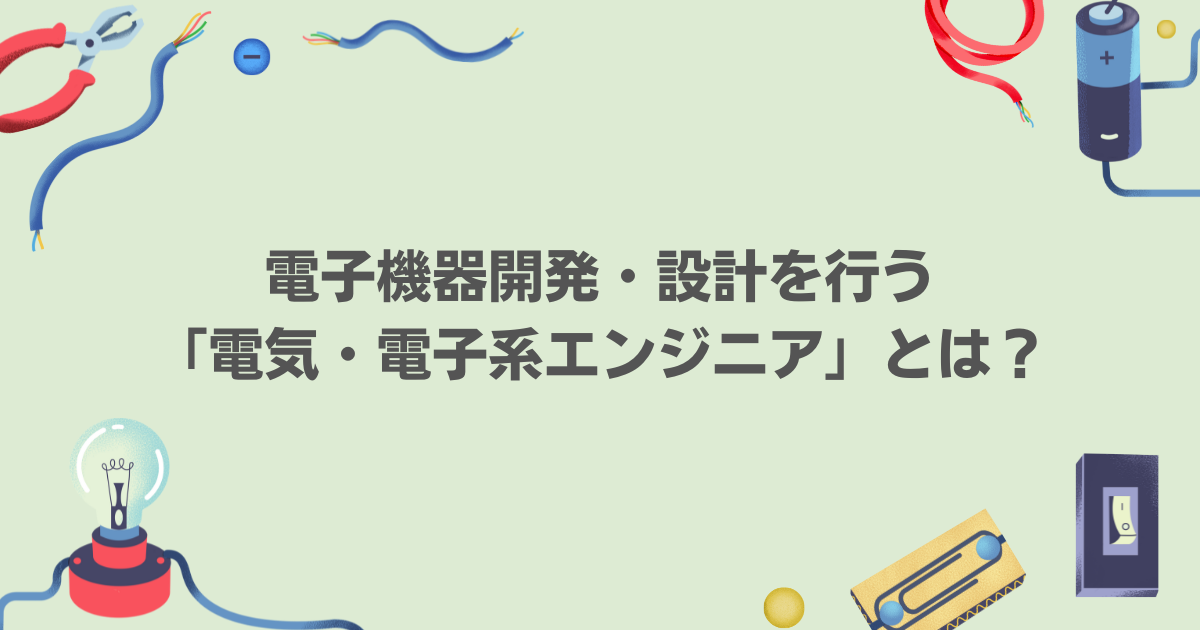
電気・電子系エンジニアは、電子機器や電子部品を用いた製品の設計・開発・製造・修理などの業務に携わる職種です。
電気・電子専門のエンジニアとして、電子機器に関する深い知識や高度なスキルを持っていることが特徴です。
パソコンやスマートフォンなどの電子機器のほか、一般家電をはじめとして電子部品が用いられている製品は数多くあります。
上述した電子機器や家電製品のほかにも、自動車から産業用機械、医療用機器などまで、電気・電子系エンジニアが対象とする製品は多岐にわたります。
ITエンジニアとの違い
ITエンジニアの業務対象の中心は情報技術です。
情報技術に関する専門知識やスキルを駆使し、システムやアプリケーションの設計、開発・運用などを担います。
業務内容によって、システムエンジニア、ブリッジエンジニア、Webエンジニア、ネットワークエンジニア、インフラエンジニア、データベースエンジニアなどに分類されます。
一方、電気・電子系エンジニアが担当する業務内容は、主に機器に組み込まれる回路の設計・開発、構築、運用です。
このように、ITエンジニアと電気・電子系エンジニアは、どちらも製品やシステムの信頼性向上において重要な役割を果たしているものの、専門とする領域や扱う技術は大きく異なります。
機械系エンジニアとの違い
機械系エンジニアに必須とされる専門知識は機械工学です。
CADやソフトウェアを使った図面の作成から、産業用機械やプラント設備、飛行機、自動車、ロケットとなどを設計するほか、製造や保守まで幅広く担当します。
電気・電子系エンジニアと機械系エンジニアでは専門分野が異なるものの、設計業務では、両者の連携によって作業を進めるケースが少なくありません。
機械系エンジニアが物理的な機械本体を設計し、電気・電子系エンジニアが電子的な制御や信号処理に特化した作業を担うことで、機械全体の性能や安全性を向上させます。
電気・電子系エンジニアの仕事内容
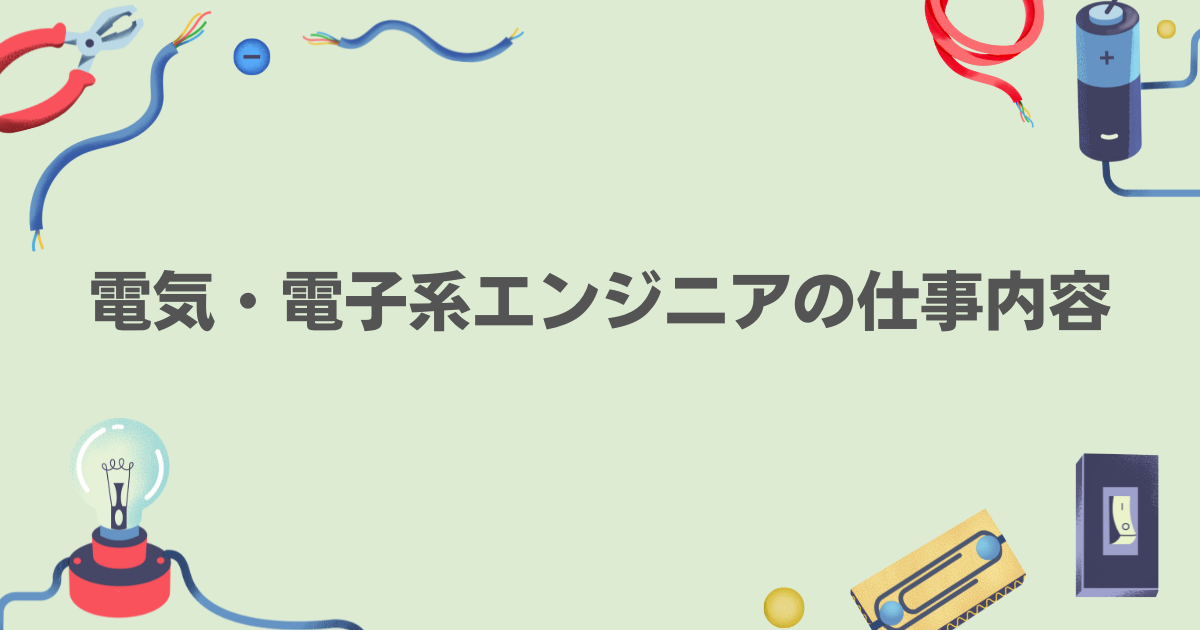
ここでは、電気・電子系エンジニアの具体的な仕事内容を、
・調査・ヒアリング
・開発計画・設計
・開発・検査・テスト
・保守
の各段階に分け、順に追って解説します。
調査・ヒアリング
製品を製造するためにはまず、顧客のニーズを具体的かつ丁寧にヒアリングしてから「どのような機器や設備が必要なのか」をすり合わせ、成果物に反映させることが求められます。
調査・ヒアリング業務が成功したか否かは、顧客の満足度によって評価されます。
実際の業務では、顧客との密接なコミュニケーションを通じて、製品開発の方向性を明確にすることが重要です。
開発計画・設計
顧客の要望を反映させて、製品の開発計画を立てるステップです。
開発計画に沿って、電気・電子機器の設計を進めていくために、まず図面を作成し、詳細な設計書を作成します。
電気・電子機器の動きや操作性、コスト面、安全性などを十分に検討したうえで、最適な設計を行わなければなりません。
開発・検査・テスト
設計書の仕様をもとに、実際の開発作業に取りかかります。
必要な資材や機材を調達し、製品を製造したのちに品質検査を行います。
検査工程には、電気・電子系エンジニアも立ち会わない場合もありますが、予期せぬトラブルが発生した際に対応できるよう、体制を整えておくことが大切です。
他分野のエンジニアと連携をとりながら作業を進め、製品の完成後は、機能性や信頼性に問題がないことをチェックする出荷前検査を実施します。
現場への設置が必要な製品の場合は、設備や配線などに異常がないか、顧客の要望どおりに稼働しているかなどを調査・確認するために試運転を行う場合もあります。
保守
製品を納品したあとも運用状況を確認し、必要に応じてメンテナンスを実施します。
長期にわたり、安全に使用してもらうためには、故障や異常への対応、定期的な保守が欠かせません。製品の信頼性は企業の評価に直結するため、エンジニアの保守業務は極めて重要です。
また、保守を通じて顧客から使用状況や要望のフィードバックを受け取り、次の製品開発へ活かします。
電気・電子系エンジニアに向いている人
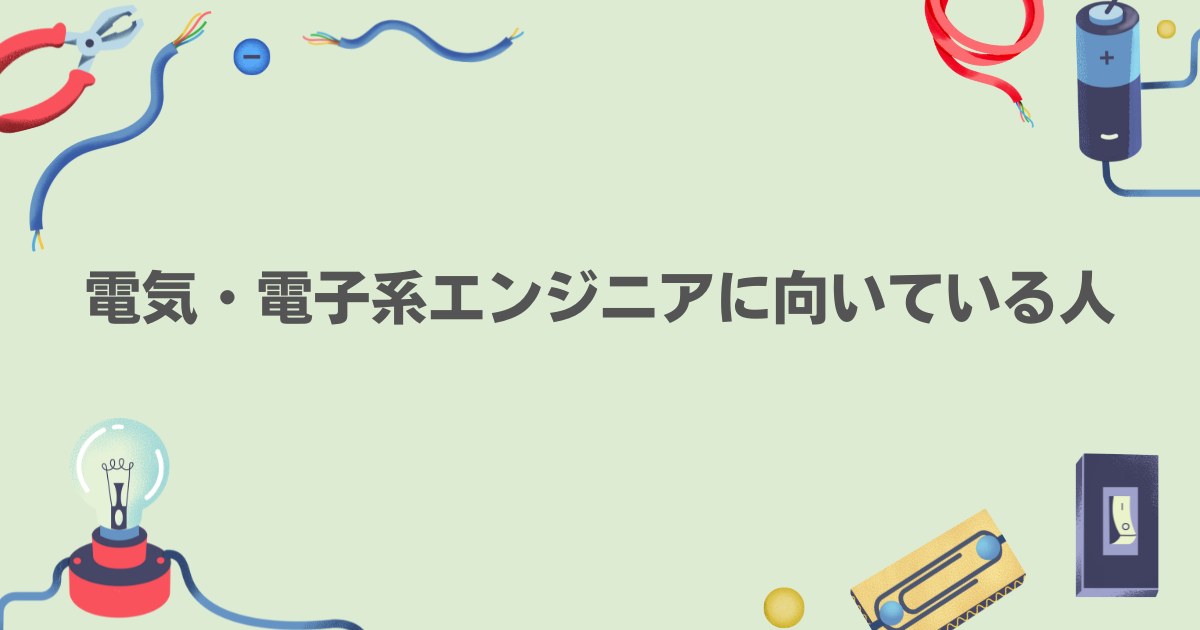
電気・電子系エンジニアに求められるのは、専門知識や技術だけではありません。
業務内容の特性上、倫理的な思考力によって解決策を見出す能力も求められます。
また、作業は基本的にチームで行うため、コミュニケーションスキルも欠かせません。
最先端技術を学び続けられる人
電気・電子系エンジニアは、日々進化する技術に対応する必要があります。
スマートフォン、タブレット、家電、自動車など生活に欠かせない機器の開発・設計に携わるため、最新の技術動向を把握し、対応することが求められます。
そのため、最新技術に関する情報収集を積極的に行い、新しい知識やスキルを吸収して専門性を高める意欲が求められます。
好奇心と探究心がある人は、技術の進化にも柔軟に対応できるでしょう。
電気工学や電子工学の知識がある人
電気・電子系エンジニアの業務には、電気工学や電子工学の知識が必須です。
回路設計や製品開発の業務では、数学、物理学、化学などの知識も求められます。
そのため、学生時代から理数系の科目を得意としている人は、電気・電子系エンジニアに向いていると考えられます。
また、業務を円滑に進めるためには、論理的思考も重要です。
日常から物事を論理的に考える姿勢は、電気・電子系エンジニアにとってプラスの材料となります。
コミュニケーション能力がある人
電気・電子系エンジニアの業務は広範にわたるため、ひとりで完結する業務は少ないです。
顧客の要望を理解し、仕様に沿った製品を開発・製造・保守するには、チームメンバーとの協力が不可欠です。
そのため、相手の意図を把握し、自身の考えをわかりやすく伝える「聞く力」と「伝える力」が求められます。
プロジェクトの進捗状況を把握し、チームの状態を読み取る能力も必要です。
知識やスキルと併せて、コミュニケーション能力に長けている人は、電気・電子系エンジニアの仕事で活躍できる可能性が高いと考えられます。
顧客や関係者との折衝、プレゼンテーション、ミーティングなどで多くの人と関わるため、日ごろから論理的思考とコミュニケーション能力を磨いておきましょう。
問題解決力がある人
電気・電子系エンジニアの業務では、設計・開発時に頻繁に問題が発生します。
そのため、論理的思考を持ち、問題解決力に優れた人材が求められています。
例えば、設計書の図面に誤りがあった場合、その問題点を特定し、適切な修正方法を考えなければなりません。
また、原因と結果の関係を明確にし、迅速に対応できる能力も必要です。
論理的に物事を考え、トラブルに対して冷静に対処できる能力は、業務の円滑な遂行に欠かせません。
粘り強く業務をコツコツと続けられる人
電気・電子系エンジニアの仕事には、設計図の作成や配線作業、回路実装など、繊細で注意力を要する作業が多く含まれます。
また、開発後には反復試験や調整作業が続き、製品として完成するまでに非常に多くの工程を経る必要があります。
そのため、細かい作業を根気強くコツコツと続けられる人は、電気・電子系エンジニアに向いています。
さらに、業務中に不具合や故障が発生した際は、その原因を特定して解決に導くための忍耐力も欠かせません。
電気・電子エンジニアへの転職で役立つ資格3選
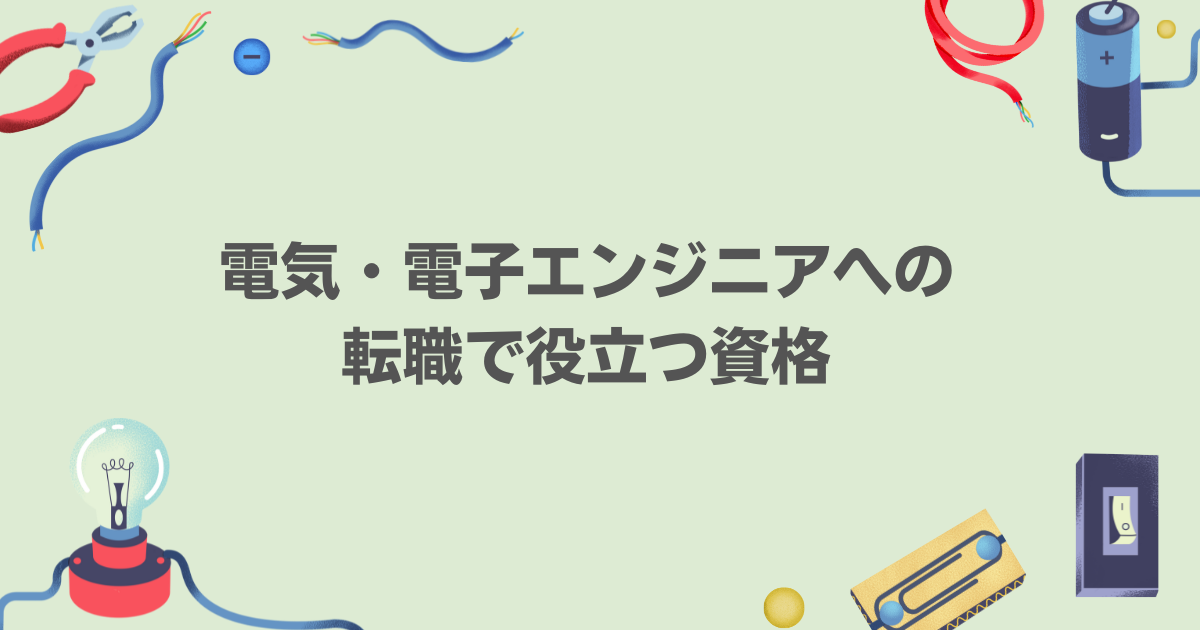
電気・電子系エンジニアに関連する資格を保有していれば、転職活動を有利に進められる場合があります。
企業によっては、これらの資格保有者に対して資格手当を支給するケースもあるため、電気・電子エンジニアに興味がある人は、ぜひチェックしておきましょう。
1. 電気主任技術者
電気主任技術者は、電気事業法に基づく国家資格であり、一般財団法人電気技術者試験センターによって実施されています。
資格保有者は、発電所や変電所、工場、ビルなどの電気設備の保安監督を担当する専門家として業務を遂行します。
電気主任技術者は、企業が事業用電気工作物を適切に保安・保守に必要な資格となるため、多くの企業で需要があります。
資格の種類は以下のとおりです。
・第一種:すべての事業用電気工作物を取り扱える
・第二種:電圧17万ボルト未満の工作物を取り扱える
・第三種:電圧5万ボルト未満の工作物を取り扱える
試験は年1~2回実施され、いずれも筆記試験のみで実技試験はありません。
1次試験は科目別合格制で、3年以内に1科目ずつ合格することが可能です。
令和5年度の合格率は第一種が17.9%、第二種が17.7%、第三種の上期が16.6%でした。
2. 電気工事士
電気工事士は、電気工事士法に基づく電気設備の工事や保守に必要な国家資格です。
資格試験は、一般財団法人電気技術者試験センターによって実施されています。
有資格者となれば、設備の設置・配線・点検・修理を行えるため、電気工事を担う企業で重宝される資格です。
なお、無資格者が電気工事を行うことは法律により禁止されています。資格の種類は以下のとおりです。
・第一種電気工事士:第二種の範囲に加え、最大電力500kW未満の工場、ビルなどの工事が可能
・第二種電気工事士:一般住宅、小規模事業所、家庭用太陽発電設備などの600V以下の設備に限定
試験は学科試験(筆記またはOBT方式)と技能試験があり、年に2回実施されます。
令和5年度(2023年度)の合格率は第一種学科が61.63%、技能が60.57%、第二種学科が59.43%、技能が71.06%でした。
3. E検定(電気・電子系技術検定試験)
E検定は電気・電子系技術者育成協議会が主催し、一般社団法人日本電気協会が後援する民間資格です。
若手から中堅技術者までを対象とし、幅広い知識とスキルを測定します。試験は電子回路、デジタル、電気回路など9分野に分かれ、レベル1から3までの難易度に分けられています。
試験は得点式となっており、分野別に正答率が開示されるため、受験することで自身の強みや弱点を把握できるのもメリットのひとつです。
レベル1の場合、正答率70%以上で合格となり「E検定 レベル1合格者」を名乗れます。
電気・電子回路の知識を証明できるため、設計者や組み込みエンジニアにも有用な資格です。
電気・電子系エンジニアに転職するならメイテックネクスト
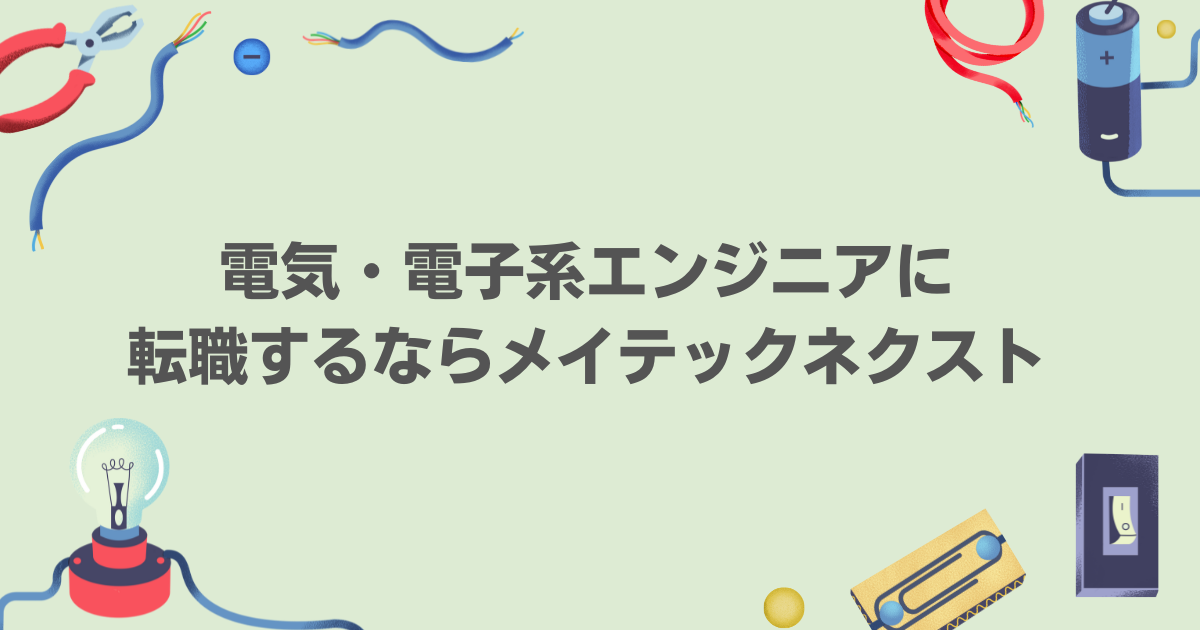
転職活動では、自身が企業の求めている人材であることをアピールすることが重要です。
しかし、電気・電子系エンジニアの転職では、どのようなアピールが有効なのかわからない人も少なくありません。
どうアピールすればよいのかわからないという場合には、エンジニア出身のコンサルタントが多数在籍している弊社「メイテックネクスト」をぜひご利用ください。
弊社には、エンジニアの求人が常時20,000件以上掲載されており、電気・電子分野への求人も充実しています。
未経験職種や業界への転職実績も豊富です。働きながら転職活動を行う場合には時間の調整が容易ではありませんが、弊社は土・日・祝日の面談も実施しており、忙しい人にも最適です。
転職を通じてキャリアアップしたい方も未経験分野に挑戦したい方も、プロの力を借りて理想的な転職を目指しましょう。
この記事の寄稿者
電気・電子系エンジニアは、電子機器や電子部品を用いた製品の設計・開発・製造・修理などの業務に携わる職種であり、電子機器に関する深い知識や高度なスキルが求められます。この職種に転職することによって、最新技術に触れられる、仕事の成果を身近なかたちで感じられるといったメリットが得られることは非常に魅力的です。転職活動をスムーズに進めるためには、エンジニアの転職に特化した「メイテックネクスト」をぜひご活用ください。技術知識に精通したコンサルタントが、キャリアアップを強力にサポートいたします。

- 香川 恵
